左ラクナ梗塞を発症し右上肢手指の運動不全麻痺を呈した症例.
- 未在代表 松舘 敏
- 2023年2月25日
- 読了時間: 3分
更新日:2023年2月26日
左ラクナ梗塞発症直後から介入することとなった方の経過を紹介させていただきます.
ある朝,起床時,右手が動かないことに気付く.手首の腱鞘炎と自己判断し経過をみることにした.
翌日,やはりおかしいと思い,救急外来を受診する.結果,左ラクナ梗塞の診断を受ける.即日,訪問リハビリテーションの相談があり,発症から3日目,初回訪問となりリハビリテーション開始となった.
初回(日)の第一印象は,右上肢帯下垂し,上肢は一塊の鋼体に観え,手部は腫脹していた.随意運動障害を呈し上肢/手指共にMMT2(Br.stage Ⅱ)レベル.幸いにも痺れ(-),感覚麻痺(-)にあった.歩行能力においては,外部観察上ではまったく問題要素は認められなかったが,ご本人の主感(知覚)にあっては「スポンジを踏んでいるような(≒ふわふわ)」とメタファーな言語表出があった.腫脹に伴う筋の伸張性低下は認められたが,病的な筋緊張は無く(腱反射亢進(-)),指節間関節の可動性を阻害する要因は認められなかった.手指5指でまんじゅうを摘まむ手指運動が精いっぱいな状態であり,スプーンで食物をなんとか運んでおり「箸で食事をしたい」を目標とした.外部観察からは指節間関節の分節的運動困難を始めとした巧緻運動障害と考察したが,ご本人の認知にあっては,自身の視覚情報よりも「指の力が入らない」と体性感覚情報が上回って訴え表出され,現在まで認知レベルに変化はなくいる.握力テストにおいても非麻痺側(左)22kg位 麻痺側 (右) 5kg位 と客観的評価においても明らかなこともあり,脳システムにおいては「運動出力系」が機能的問題と考察し,まずは「視覚情報-関節覚の統合」から導入することとした.
発症から1週間半を経過する頃には,母指から小指への指折り運動が出現可能となり,脳の機能解離が解消し始めたのではないかと考察した.
その後,段階的に「表在覚-関節覚の統合」「指節間関節-指節間関節の空間的統合」「体性感覚からの運動イメージ構築」「運動イメージ下での段階2へ」「物品形状と表面性状-関節運動コントロール」と運動出力に働きかけていった.
今症例の経過紹介を記載している今日は,発症して1ヶ月となる.うれしいことではあるが私の予後予測に反し,基本的なとこでの巧緻運動障害は改善し,握力テストは麻痺側(右)5kg位 ⇒ 26kg位と回復した.しかし,ご本人の「指に力が入らない」の認知表出は以前として聞かれている.手指運動の改善とともに上肢運動も改善認められ,また下肢のメタファー表出も解消している.これも創発特性なのかと思考過程中にある.
ご本人の希望の1つである「早期卒業(リハビリテーション終了)」に向けて,作業療法(箸の操作練習)を提案し開始している.練習は訪問1回の段階だが,開始日にあっては上手に使っておられ,当初提案した練習期間1ヶ月を待たずに「卒業(ゴール)」となりそうである.
脳機能の問題(脳の損傷)が軽症にあったことは言うまでもありません.ただ私としては,発症直後から介入できたこと,そのため過剰な刺激による二次的機能障害(筋緊張亢進)が無く認知神経リハビリテーションを導入できたことが改善につながったと考察しています.
未在代表 松舘 敏



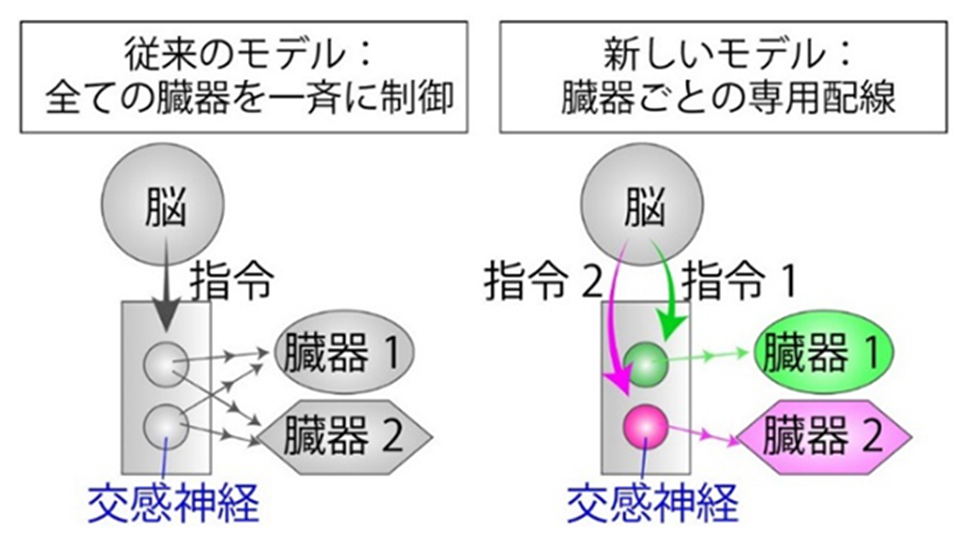


コメント